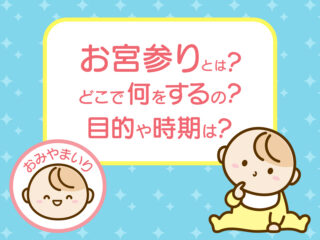お宮参りはいつ行く?ベストな時期は生後〇ヶ月!【お宮参りの時期】

今回は、「お宮参りへ行くベストな時期」について解説します。
「お宮参りは、いつすれば良いの?」「お宮参りの時期が知りたい」という方の疑問をスッキリ解消します。
本記事は、このような方へ向けて執筆します。
- お宮参りをいつにするか検討中
- お宮参りのしきたりや風習がわからなくて悩んでいる
- 一生の思い出になる記念の行事なので、失敗したくない
この記事を読めば…
- 赤ちゃんやママのこと、写真のことなど、多方面から考えた結果の「お宮参りベストな時期」が、わかる
- お宮参りに行く時期を決められる
この記事は、数多くの伝統行事に関わってきたスタジオGRACEカメラマンが執筆しています

馬場みのり
お宮参りの時期は、地域や宗教によって違うため、誰かに尋ねてみても答えがあいまいなことが多々あります。
ネットで調べてみても「ママや赤ちゃんの体調を優先して…」などの記載が多いです。
では、「結局、いつが良いの?」って疑問ですよね。
そんな方へ、今回の記事ではズバリお答えします。
■この記事では、以下の内容で、順に解説します
- お宮参りベストな時期 トータルで考えた結果
- その理由
- 一般論も知識として知っておこう
- お宮参りは いつまでに行くべき?
- お宮参りの日程を決めるときの注意点
はじめに
お宮参りは、言い方がいろいろあります。
神社へ行く場合は、
- お宮参り/宮参り
- 初宮詣:はつみやもうで
- 初宮参り:はつみやまいり
など
お寺へ行く場合は、
- 初参り:はつまいり
- お初参り:おはつまいり
など
本記事では「お宮参り」で統一して記載します。
お宮参りベストな時期 トータルで考えた結果
お宮参りに行くベストな時期は、
- 生後2~3か月頃
もう少し詳しく言いますと、「赤ちゃんが笑うくらい成長したころ」が良いです。
この「笑う」は、新生児の生理的な顔の神経の反射ではなく、自発的に笑う「社会的微笑」のこと。
パパやママが笑いかけると、赤ちゃんも笑顔を返してくれるようになる頃が、お宮参りに行くベストな時期です。
※ 昔からの「しきたりや風習」「宗教上の決まり」などに、こだわらないという方への おすすめ時期です。
お宮参りは日本の伝統行事ですので、しきたりを重んじる方や、宗教上の決まりがある方は、それに従うのが良いでしょう。
その理由
お宮参りに行く時期を生後2~3か月にすると、たくさん良いことがあります。
では、順番にご紹介します。
赤ちゃんやママにとってのメリット
- 生活のリズムが出来てくる
- 授乳時間の間隔が長くなる
- 帝王切開の傷が癒えてくる
- 育児に慣れてくる
- 余裕をもって必要な物の準備ができる
これらの理由で、ママや赤ちゃんが、お出かけしやすくなっています。
お宮参りに必要なものリスト⇒ このまま使える!お宮参り持ち物リスト
写真撮影でのメリット
- 声や音に反応してくれるため、カメラ目線が撮りやすい
- 起きている時間が長くなる
- 感情やお顔の筋肉の発達により「笑顔」も時折見られる
- お肌がきれい ※1
これらの理由で、お宮参りの写真撮影もしやすくなっています。
※1 新生児は母体から移行する性ホルモンの影響で皮膚トラブルが出やすくなっています
この他のメリット
この他、赤ちゃんの首がしっかりしてくるので、
- お祖父様やお祖母様も、赤ちゃんを抱っこしやすくなる
- お祖父様やお祖母様も、赤ちゃんのお世話をお手伝いしやすくなる
といったメリットもあります。
赤ちゃんをみてくれる人が多いと、お宮参りは、グ~ンとラクになります。
一般論も知識として知っておこう
お宮参りは、一般的には、赤ちゃんが産まれてから生後1か月頃に行う行事とされています。
お宮参りとは
お宮参りとは、簡単に言いますと、その土地の産土神/氏神様をまつる神社へ参拝し、ご祈祷を受けること。
- 赤ちゃんが無事に誕生したことのご報告をする
- 神様に感謝の気持ちを伝える
- これからの健やかな成長を祈願する
お宮参りですることや、目的などは、「お宮参りとは?」をご覧ください。
初穂料は、「お宮参りの初穂料について」に詳しく記載しています。
時期について、細かく言いますと
- 男の子は生後31日目(または30日目)
- 女の子は生後33日目(または32日目)
と言われています。
神社庁のホームページ、「出産と育児に関する神事について」のページでは、男の子31日、女の子33日と記載されています。
しかし、お宮参りの時期は、地域や宗教によって異なるため、これと違うところもあります。
お食い初め(百日祝い)とお宮参りを一緒にする地域もあります。
※お食い初めは生後100日~120日に行う行事

馬場みのり
お宮参りを神社で済ませ、その後、自宅やホテルでお食事の際に「お食い初め」を行うご家庭も多いです。
2つのお祝いの行事を1日で済ませられるのは、良いですよね。
お食い初めとお宮参りを同時にするやり方や注意点は、コチラの記事でご紹介しています。
参考:出産と育児に関する神事について | 神社本庁 (jinjahoncho.or.jp)
生後〇日、いつからが1日目?
赤ちゃんの生後〇日は、数え方が2パターンあります。
- 産まれた日を1日目とする(日本古来の数え方)
- 産まれた日を0日目とする(現在主流の数え方)
現在では、②の「産まれた日 =0日」が主流ですが、
日本古来の伝統行事では、①の「産まれた日=1日目」で数えます。
ですので、お七夜、お宮参り、お食い初めなどは「産まれた日=1日目」として数えましょう。
・
お宮参りは いつまでに行くべき?
お宮参りの時期は、いつまでという期限は、ありません。
生後3か月以降~生後6か月頃に行うご家庭も多いです。
私たちがお宮参りの撮影をしていて、実際に多い順は
- 生後2~3か月頃
- 生後1か月前後
- 生後4か月~6か月
の順です(地域は関西)
ご家庭の事情により、生後6か月~1歳になるまでに行うご家庭もあります。
お宮参りの日程を決めるときの注意点
お宮参りは、パパ、ママ、赤ちゃん、ご両家のお祖父さま、お祖母様の皆さんが参加される行事です。
しきたりを重んじるご家庭もありますので、時期や日程については皆様で話し合って決めることも大切です。
また、気をつけたい点が4つあります。
- 赤ちゃんが大きくなると体重が増え、長時間の抱っこが大変
- 赤ちゃんは成長とともに動きたい欲求が強くなる
- 七五三シーズンと重なると人気のある神社は大変混雑する
- 七五三シーズンの週末、「大安」の日は混みあうことが多い
という点です。
これらの対処方法は、
- 必要に応じて、抱っこ紐を利用する
- 時間のかかるご祈祷はやめて、普通の参拝にする
- 七五三シーズンなら平日や午後にする
- 六曜を気にしないなら「大安」を外す
などがあります。
抱っこ紐については、『お宮参りは「抱っこ紐」があると便利!おすすめの抱っこ紐は?』をご覧ください。

リッキーさん
ご家庭により、風習やならわしを大切になさることもありますので、お宮参りの時期については、ご家族、ご親族の皆様と相談されたほうが良いでしょう。

馬場みのり
赤ちゃんが大きくなると
- 体が大きく重くなるため長時間の抱っこがしんどい
- 動きたい欲求が強くなり、長時間じっとしているのは難しい
ということがあります。
ご祈祷で、お祖母様が長時間抱っこするのが、ご負担になるようでしたら
- 普通の参拝だけにする
- 抱っこ紐を使う
- 代わりにママが抱っこする
などの対処が必要です
六曜は気にしないで大丈夫!
お宮参りは「大安が良い」などと言われていますが、六曜は神道にも仏教にも関係がありません。
ですので、気にしなくても良いのですが「大安のほうが縁起が良さそう」「どうせなら吉日に行きたい」という方も多いです。
仏滅は「それまでのものが滅び、新しく物事が始まる」という意味もあり、物事を始めるには良い日だという人もいます。
あまり六曜や縁起を気にしないなら、仏滅は神社が空いているというメリットもあります。
六曜については「お宮参り「大安」「仏滅」など六曜は気にするべき?」で詳しく解説しています。
・
真夏や真冬のお宮参りは…
- 気候のきびしい季節は、無理せず避けるほうが良いでしょう
夏ですと、体温が高い赤ちゃんにとって、白羽二重やベビードレス(セレモニードレス)、その上に襦袢をつけたお祝い着(のしめ/お宮参り着/産着)を着用させるのは、暑くて、かわいそうですよね。
また、ママやお祖母様が、留袖や訪問着など正装でお参りしたい場合、夏用の着物もあります。
しかし、服装だけで暑さ対策するには無理がある真夏は、避けたほうが無難。
冬は、和装でも洋装でも、コートやおくるみで調節できそうですが、体温調節機能が発達していない赤ちゃんと外出するのは心配。
やはり真冬も避けたほうが無難です。
お宮参りの時期をずらすのはマナー違反になる?
- お宮参りの時期をずらしてもマナー違反ではありません

お宮参りって生後1か月頃に行くって聞いたんだけど…
時期をずらしてもマナー違反にはならない?

馬場みのり
はい、大丈夫です!
- 産後のママの体調が不安な場合
- 赤ちゃんの体調が優れない場合
- 気候が厳しい場合
- ご家族のスケジュール調整ができない場合など
日程をずらしてお宮参りされる方は多いです。
また、お宮参りを予定していた当日でも、急に赤ちゃんやママの体調が悪くなるケースもあります。
ご両親や旦那様のご都合もあると思いますが、決して無理をせず予定を変更しましょう。
喪中・忌中の場合は?
忌中のときは…
身内に不幸があり、忌中のときは、忌中明けまで神社へのお参りは控えます。
お寺での「お初参り」は忌中でも大丈夫ですが、お祝い事を控えることが多いです。
忌中・喪中のお宮参りについては『お宮参り「喪中」のときはどうすればいいの?』で詳しくお伝えしています。
お宮参りに行けそうにない場合は…
お宮参りに行きたいのに、なかなか行けない…という方へ
- 育児でバタバタしていて、お宮参りに行けない
- 家族のスケジュールが合わなくて、お宮参りに行けない
- 両親が遠方でタイミングが合わず、お宮参りに行けない
など、いろんな事情で、お宮参りに行けないまま 時間が過ぎてしまうことがあります。
そんな時は、
- お宮参りの記念撮影だけでも済ませておくと安心
記念撮影だけなら写真館やスタジオがおすすめ
写真館やスタジオで、赤ちゃんの写真だけ撮ってもらうなら、気楽に行えます。
産着がレンタルできるお店なら、持ち物の準備もなくてよいので、手軽に行えます。

なかなかスケジュールが合わなくて、お宮参りに行けず、
赤ちゃんがどんどん成長しちゃいそうなんだけど…

リッキーさん
そんな時は、写真館(フォトスタジオ)で記念撮影を先にしておくのもひとつの方法です。
スタジオ撮影なら、季節や天候も気にしなくて大丈夫!
一生の思い出に残る素敵な写真が撮影できます。

馬場みのり
お店によっては、いろいろなセットやプランがありますが、
必要なカット数だけ撮ってもらえば、料金も高くありません。
写真館は出張撮影より金額の相場が高いと思われがちですが、
衣装を貸してくれるところも多いので、衣装を購入したりレンタルする費用を考えれば、決して高くないですよ。
出張撮影の場合は…
家族そろってのお宮参りとは別に、神社で記念撮影だけされる方もいらっしゃいます。
その場合、注意することは、
- 必ず事前に神社へ電話して写真撮影OKか確認が必要
商業カメラマン ( お金をいただいて撮影するカメラマン )による撮影を禁止している神社もあります。
また、神社はお参りをする場所ですので、他の参拝者にご迷惑にならないように行動しましょう。
補足・トラブル回避のために…
当店でも、天候やご家庭の事情により、ご祈祷とは別の日に神社で記念撮影をすることがあります。
しかし、「参拝やご祈祷を全くせずに神社で撮影だけする」という行為は神社に対して、大変失礼にあたります。
神社は神様をおまつりしている神聖な場所。
撮影するために用意された場所ではないし、私有地です。
公園のように使ってはいけません。
また、公園でも管理者はあるので、撮影で使用する際は撮影しても良いか確認しておきましょう。
特に商業カメラマンを使う場合は、どこでも許可なく勝手に撮影していると思わぬトラブルに発展することもございます。
※本来ならカメラマンが撮影許可の確認や手続きをするのですが、最近はそういったことをきちんとしない方が増えておりますのでご注意ください。
・
★★★★★
子育てでケータイを使う時間が減ったなら楽天モバイルに乗り換えよう!
使わなかった分は、勝手に料金が安くなる♪
ポイントも貯まるし、貯まったポイントでケータイ代を0円にすることも可能。
↑↑↑
詳しくはバナーをクリックしてご覧ください。
他社との比較表もあって、わかりやすい♪ 乗り換えは簡単3ステップ!
・
・